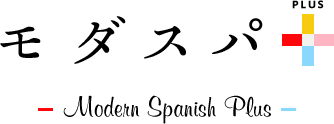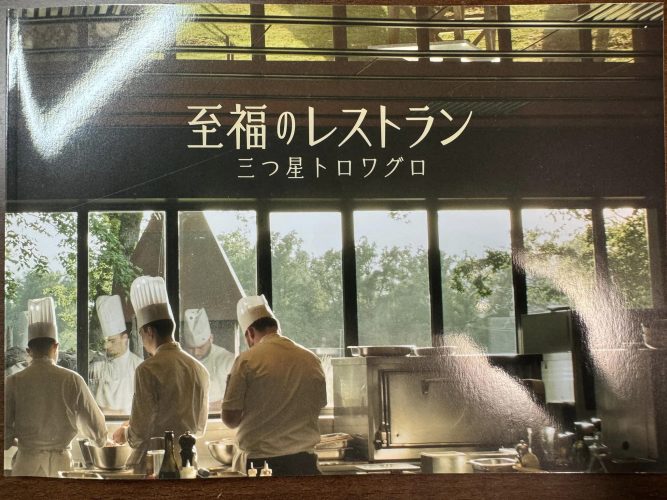フェラン・アドリア、マッシモ・ボットゥーラ、そして、たったいま世界1位を獲得したばかりのミツハル・ツムラ…
それは特別な空間だった。ベスト50で何度も1位を獲得した歴代のグランシェフと、今年誕生したスターシェフたちがひとつの壇上で喜びを分かち合っている。
2025年6月、イタリア・トリノで開催された「世界のベストレストラン50」2025年の授賞式。恒例となった、授賞式のフィナーレを飾る集合写真撮影の様子を、私は客席で見ていた。
23年間で11軒の「世界一」を生んだこのイベント、「アイコン・アワード」を受賞したマッシモ・ボットゥーラ氏をはじめ、今年は過去に世界一位を獲得したシェフも招待されており(彼らは他の受賞シェフと異なり、紫のタイを巻いていた)、この壮観な眺めが展開されたのだ。
会場となったトリノ郊外リンゴット・ホールを包む熱気に身を委ねながら、一方で、かれこれ16年ほどこのランキングを見てきた野次馬として、なぜかかすかな違和感、隔たりを感じている自分に気がついた。
その「隔たり」の正体は、実は意外なところにあった。

「世界のベストレストラン50」は2002年、英国の雑誌社の編集部員のある冗談から始まった。
「英国のレストランの頂点を決めるランキングを作ったらどうだろう」
その話がきっかけで始められたこのランキング。英国のレストランの頂点を決めるより世界の頂点を決めたほうがインパクトが大きいからというのが理由だったという。しかしこれが現在、世界中でこれほど影響力を持つと予想していた人は当時どれくらいいただろうか。
最初はリストの発表だけ。アワードセレモニーが始まったのも2年目からだ。
世界1位というのは特別な価値を持つ。ともすれば、ミシュランガイドの三つ星よりも世界中の注目を集めることになる。三つ星は世界に157軒あるが(2025.7現在)、世界1位は当たり前だが世界で1軒しかないからだ。
2013年と2015年に1位を獲得したレストラン「エルセジュール・カン・ロカ」(スペイン)のジョアン・ロカ氏は、「授賞式から24時間以内に、200万件もの予約リクエストがあった」と語っている。
初年度(2002年)の世界一位はスペインの「エル・ブリ」。
「エル・ブリ」はその後計5回、そして2010年に世界1位を獲得した「ノーマ」も5回の1位を獲得。「エル・ブリ」は分子ガストロノミーの騎手となり、「ノーマ」は新北欧料理を根付かせるなどのさまざまな新機軸の一つ一つが世界の注目を集めた。そうして世界中のレストランに影響を与えていったのはご存知の通りだ。
特に「ノーマ」はデンマーク全体の経済にさえ影響を与えた。「ノーマ」の世界的な知名度は地元サプライヤーの活性化や雇用の創出、観光への波及効果をもたらし、コペンハーゲンと主要都市の観光客数は最大11%増加し、「ノマノミクス」ということばさえ生んだほどだ。
影響はそれだけではない。デンマークをはじめとした北欧は「ノーマ」の成功以降、美食大国とでも呼ぶべき様相を呈している。「ノーマ」出身者などの新店が近隣に生まれ、新人料理人の登竜門である「ボキューズ・ドール」においても、北欧勢の勢いはいまだ衰えをみせない。
これらのレストランの成功が引き寄せたのは観光客だけではない。世界中の野心的な若い料理人たちを、スペインへ、またデンマークへ惹きつけるきっかけとなった。そのことが、デンマークのレストラン業界のレベルアップに大きく寄与したであろうことは容易に想像がつく。
その注目を集める重要な要素として、毎年毎年このランキングによって「世界一位」とアナウンスされることの効果は絶大だったに違いない。
その世界1位というアナウンスが、2019年に大きな転換点を迎えることになる。
「ベストオブベスト」いわゆる「殿堂入り」は、「世界1位を1度でも獲得すれば、次年度からはランキングから外れる」というシステムだ。
「殿堂入り」のルールがなぜ生まれたのか。
実はこれは、過去に1位を獲得した複数のシェフ側から提案されたものだったという。
1位を獲得すれば、いつか1位でなくなる日が必ず来る。その際に、スタッフの士気が下がる、また、シェフ自身も精神的にポジティブさが保てないというのがその理由だ。
しかし当事者であるシェフだけでなく、ランキングを見る側としても、そのルール変更にはある程度の必然性があった。毎年同じ店が世界1位というのでは、ランキングに新味が出ないからだ。
あれから6年。
ルール変更以降、1位を取った店をならべてみる。
| 年度 | 店舗名 | 国名 |
| 2019 | ミラズール | フランス |
| 2021 | ノーマ | デンマーク |
| 2022 | ゲラニウム | デンマーク |
| 2023 | セントラル | ペルー |
| 2024 | ディスフルタール | スペイン |
| 2025 | マイド | ペルー |
2021ノーマは移転・改装してリセットと見なされたため
考えてみよう。もしベストオブベストのルールがなかったら今のランキングはどうなっていただろうか。まだノーマが世界1位で、ディスフルタールが2位で…という感じだろうか。
殿堂入りという制度、考えてみればかなり変だ。ランキングの正当性より新味を出すことが優先されるということだからだ。ランキングが根底から存在意義を問われるといっても過言ではない。
しかしなぜかこの制度、とても自然に人々に受け入れられた。「ベストオブベストはやらない方が良かった」という意見を聞いたことがない。
それはとりもなおさず、人々はこのベスト50に本当の順位とは別のものを求めているということだろう。それはやはり、毎年違うものが見たいという欲求が、正確なランキングが見たいという思いを上回ったということではないだろうか。
ところで今回、授賞式をめぐる一連のプログラムの中で、イタリア「レ・カランドレ」のシェフ、マッシミリアーノ・アライモ氏が、「流動性」という考え方を紹介していた。アライモ氏は2013年に、アートブックのような豪華な料理本『流動性(Fluidità フルイディタ)』を出版している。水を張った容器越しに料理を写した、ユニークな写真が特徴だ。

アライモ氏は「かつて私たちが目にする多くのものにあったある種の神秘性が薄れ、今日ではあらゆる情報、レシピ、調理工程、動画などに自由にアクセスできるようになっている」と語り、食材がどのタイミングで加わり、他の食材とどう関係するかの重要性を強調していた。彼が調理で重視するという「流動性」は、日々変化する食材への尊重にもつながっている。
すべてのものは変化する。ヘラクレイトスの「万物流転」の法則は、国境がオープンになり、知識や考え方の共有が促される今の時代にはより強く感じられる。しかも、その速度は以前よりさらに速くなっているのではないだろうか。
そうであるならば、ランキングも毎年動くのが自然と感じてしまうのかもしれない。私たちの意識も変わっていくのだから。
(本文は下に続きます)
世界のベストレストラン50については、こちらにも記事を書きました。
世界1位を獲得した「ニッケイ料理」とは? 「世界のベストレストラン50」から見るレストランの「いま」(東洋経済オンライン)
1位の店が毎年変わる、それは何を意味するか。
それは言いかえれば、圧倒的な一位が生まれないということでもある。かつてのエルブリやノーマのように、何年も1位に君臨し、世界中の若い料理人をその国や都市に惹きつけるもの。
世の中は多様性を重視する、「すべての人を取りこぼさない」方向に進んでいる。SDGsの考え方にもある環境の持続可能性、また人材の持続可能性については今回世界1位を獲得した「マイド」のツムラ氏の発言にもあった。
もし、日本のあるレストランが何年も世界1位を獲得し続けたらどうだっただろうか。おそらく世界の観光客にとって、また若い料理人にとって日本は今よりもっと憧れの国となり、厨房には各国の料理人が溢れていたのではないだろうか。
でもおそらく、それは起こらない。時代が変わってしまったのだ。
私が壇上のシェフたちに感じた隔たりとはそれだった。ランキングも流動する。紫と赤のタイは、その前か後かということを、明確に示す記号のように感じられたのだ。
そうしてみると…と、また考える。
新しい美食大国はもしかして、もう生まれないのではないだろうか?
その代わりに、きっと私たちが手に入れたものがある。
新しい何かは、これからは、さまざまな場所から生まれるのだ。