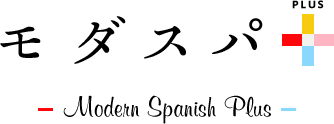シェフとしてどこで店を構えるか。
東京など都市部、また地元に戻って開業という選択肢を選ばず、さまざまな理由で、これまで縁のなかった場所を選ぶ人の例を最近多く耳にするようになりました。
その範囲は日本国内にとどまらず、海外にも及びます。
そんな例として、シンガポールで働く2人の若手シェフにインタビューしました。
シンガポール「ホワイトグラス」の山下拓也さんと、「オマカセ・スティーブン」の窪田修輔さんです。
以下の文章は、そこで話された内容のざっくりとしたまとめです。
お2人の話された内容には重なる部分もあり、まとめた方がより理解しやすいと思いました。
この記事を書くきっかけになったインタビューはこちら
前編 「ホワイトグラス」山下拓也さん
後編 「オマカセ・スティーブン」窪田修輔さん
山下さん、窪田さんのお2人とも、もともとシンガポールにはゆかりがなく、オファーを受け初めてこの地を踏んだ人たちです。
2人ともたまたま、初めてシェフとなるのが海外でした。
何もわからない状態から異国に飛び込む決断には、勇気が要ることだったと思います。
海外で働くことは、国内とは異なるどのような事情があるのか。
整理すると以下の2つの面に集約できるように思いました。
労働の側面
創造物としての側面
前提として押さえておいた方がよいことが2つあります。
①料理を作ることは労働であり、②料理はシェフの思いをのせた創造物でもあるということです。

海外で働く際に注意すべきポイントとして記事で話されたことを箇条書きにまとめると、以下の3つです。
・契約書
・ビザ
・スタッフやオーナーとの関係
海外で働くときには、日本での就労ではあまり意識することのない点が問題になってくるようです。
お金を稼ぐ労働という側面と、自分を表現する創造物を創るという側面。
契約書ではそのどちらか、あるいは両方についての項目があり、それはオーナーによって濃淡がさまざまであることが、お2人の話からは読み取れます。
また、どんな店にしたいかのビジョンをオーナーが持たない、あるいは意識できていない場合があるという指摘は重要だと思いました。
もしそれが契約の時に明文化されておらず、働き始めてからその食い違いが判明した場合は双方ともに悲劇です。
「料理について、経営についてのお互いの認識度合いが事前にわかるアイテムが契約書だ」といえるのかもしれません。
記事では、契約書に日本では考えられないような非常識な内容が盛り込まれている例も紹介しました。
お2人とも幸いにして良いオーナーと巡り合ったとのことですが、契約書にはいろいろなパターンがあるようで、どんなに非常識な契約であろうと、いったんサインしてしまえば履行の義務があります。
またそれに違反した場合に(それが非常識な契約内容であれば)財産を削られたり次の仕事ができなかったりするような、生活の根幹にかかわるリスクを受ける可能性があるのも重要な点です。
海外でシェフになってスタッフを雇ってみて「日本人はよく働く」とは、今回取材した2人が口をそろえて語っていたことでした。
個人差はあるにせよ、スタッフの労働観にも国民性が出るようです。
それならばスタッフにも日本人を雇えばいいかというと、簡単にはいかないようです。
シンガポールでは、就労ビザの種類によって支払う最低給与額が決まっています。
日本人が取れるビザとしては大きく分けて「EP」と「エスパス」がありますが、いずれも月給の条件として最低5000シンガポールドル(日本円約50万円)、配偶者帯同だと6000シンガポールドルが必要です。
給与はガラス張りで、無給や、極端な低賃金には最初からできない仕組みです。
海外で日本人を雇うのは容易ではないもう一つの理由は、どの国も自国民の利益が最優先で考えられているからです。
記事には入れられませんでしたが、実際に日本人を雇う際には、まずシンガポール人向けに求人を行い、そこで人員が集まらなかったというエビデンスができてはじめて、外国人(日本人)に求人を出すことが出来るのだそうです。
どの国も自国民の利益を優先で考えるので、
「自国民(この場合はシンガポール人)の雇用を満たすべきところをなぜ日本人を雇うのか?」
ということを行政に説明して納得してもらう必要があるといいます。

一方で、料理が創造物であることに目を転じると、また別のものが見えてきます。
まず、お2人が共通して語っていたのは、「四季は料理を作る上での大いなる恵みだ」ということ。
食材に旬があると、その旬によって厨房に並ぶ食材が日々変わり、それらが日々の料理に動きを生みます。
一方で海外では、四季という感覚が薄い国、またほとんどない国も多いです。
四季という感覚がリアリティを持つのは、訪れるゲストもまたその季節感とともに生きているからでもあります。
たとえば、早春の料理にふきのとうが並べば、皿の上から春を感じる。
ジビエが出始めれば、冬の訪れを感じる。
そのような季節感を反映した料理に共感できるためには、共通認識としての季節感を料理を提供する側とゲストの両方が持っていることが必要です。それは日本では当たり前に「あるもの」と感じてしまいがちですが、海外では必ずしも当たり前のことではないのだと気づかされます。
窪田さんは「日本みたいな季節感がないので、食材の本質みたいなところに触れられないのはしんどい」と語っています。
また、これは少々微妙な話になりますが、
自分の国の(その国の)食材をストーリーとして受け取れるだけのリテラシーが食べ手に備わっているか?
ということも考える必要があるような気がします。
その食材が、いつ・どこで採れて、どのように調理された結果いま自分の目の前にあるのか。
それを想像する楽しみは、一朝一夕では生まれないし、むしろ、ないことの方が当たり前なのではないか…とも考えさせられます。
労働の面と創造物としての面。
これらは海外でのみ問題になることでなく、日本にいても考えるべきものなのではないかと思います。
「日本での当たり前」は、海外では当たり前でないこと。
海外だからこそ、日本の事情や良い点に気づけること。
それがわかるのは、海外に出るメリットのひとつといえます。
むしろそれをよりはっきりと見せてくれることこそが、海外で働く意味なのかもしれません。
「海外に出る・海外で働く」という話題、昨今は給与の高さばかりが多く話題になりますが、それだけでないメリットやデメリットがあるとわかりました。
それらを頭に入れたうえで、海外で働くことと日本で働くこと、その二つはフラットな二択として考えても良いように思います。