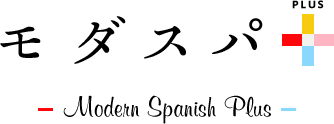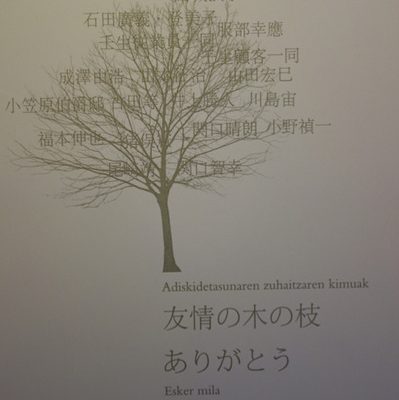訪問したのは12月末。
オープンしてまだ2か月なのに、すでに予約が取れなくなっていた。
logyは、東京・青山のレストラン・Florilege(フロリレージュ)の姉妹店だ。
店名になったlogyとは「テクノロジー」など語の末尾につく接尾辞だ。
「何かと合わさって、別のものになる」というニュアンスなのだろう。
シェフは田原諒悟さん。
イタリア料理を経て、フロリレージュで長年スーシェフをつとめていた人だ。
フロリレージュのシェフ川手寛康さんがイベントなどで不在の時に、いつもはスーシェフの田原さんがシェフとしてイタリア料理を出すイベントを行っていて、すでに田原さんの料理を知っている人も多いようだ。
客席は14席くらい、個室が1室。
中央の厨房を囲む形式は、フロリレージュと同じ。
ゲストはほとんどローカルだというが、この日は日本人ゲストがもう2組くらいいた。
コースは約10品。
食材はほとんどすべて、台湾のものを使っているそうだ。

ホッキガイ
田原さんの出身地・北海道の名産で、田原さん自身が思い入れのあるホッキガイ、今回のものは台湾産だ。
ソースは2種類。タイ風味のソースと、ヨーグルトソース。
タイ風味のソースはライムリーフ、生姜、唐辛子などが入って香りを足し、ヨーグルトのソースは酸味と乳酸のうまみを足している。普通のヨーグルトより、酸味が強調されている。
ソースがかかっているので見た目はフランス料理だが、香りが台湾だ。
台湾のラディッシュが独特の「はみ出し感」を持つ。
台湾の野菜は、日本のそれより野性味が強い。

アマダイ
松笠焼きでうろこはカリカリ、中はしっとり。
これも、ひと口食べるとソースが台湾の香りだ。
付け合わせは台湾シシトウと、台湾バジル。
上に載っている黒い果実は金柑の一種で、金桔(チンチー)という。
それを黒焦げにしているのがポイントで、酸味も香りも強い柑橘を、黒焦げになるまで火を入れることで、そのまま齧れるくらい、やわらかな酸味になっている。
五香粉の香りが台湾っぽさを強調している。
余談だが、金桔のジュースを、以前、迪化街のジューススタンドで飲んだことがある。
作り置きではなく、屋台のリヤカーに皮つきの生の柑橘を山のように積んで、注文するとその場で勢いよくミキサーにかけてくれるのだ。
日本のみかんや金柑より、こちらの柑橘は総じて酸味が強い。
常時暑くて汗をかく台湾では、このくらいキリッとした酸味の方が快く感じられる。

サワラ
熟成9日。
うまみを強めたサワラに添えられたソースは、ブールブランのソースと、香菜のソース。
2つの要素が、サワラを媒介として混ざり合っている。これも、2種類のソースでないとできない味わいだろう。
ここに足されている揚げた桜海老。天かすのような細かい粒に、台湾っぽい香りがする。
先ほどのアマダイもこのサワラも、熟成をかけているとはいうものの、素材そのものの味が比較的おとなしめ。
その代わり、それを補うように、いろいろな香りが載っている。
素材の味がおとなしめということは、いろいろな付け合わせやソースを載せる余白があるということでもある。

うずら
うずらの胸肉ともも肉。2種の部位を2種の調理法で。
焦がしバターのソース。台湾の赤米、コメのチップス、付け合わせの野菜にわずかな酸味がある。
もも肉を覆う葉は、サツマイモ。
表面の照りの焦げから、火入れの確かさが伝わる。
うまいなあ。
台北のダイニングで食べているのは、確かにフランス料理。
でも日本やフランスとは明らかに違う、台湾の香り。
日本で食べる繊細さと、台湾の、あちこちはみ出す個性が、フランス料理という箱のなかにおさまっている。
以前体験した台北・Tairroirでの3か国イベントのときとも、料理の方向性が異なるのが興味深かった。
あのときは、国籍が異なる3人のシェフが日程を合わせてひとつのコースを作る非日常感・祝祭感があったが、今回はもっと台湾の日常の食が感じられるテーブルだ。
いま、国や地域をまたいだ往来が加速し、ボーダレスな時代になってきている。
航空券の値段が下がり、人の往来がしやすくなった昨今、
「A どこの国で」「B どこの国の人が」「C なに料理を作るか」
という3つの要素がすべて異なる事例が、最近は珍しくなくなってきたように思う。
また、これらの複雑に入り混じってきた要素を後押ししているのは、輸送技術の発展や物流の流動化だ。
たとえば香港やシンガポールでは、日本の食材が週に6日入ってくるのだそうだ。
築地(豊洲)市場あるいは、北海道や九州など各地方の生産者から直接食材をとりよせる。
日本以外の国において、日本と同じ食材で料理を作るハードルは、素人がはたから見ていても、ずいぶん下がったと思う。

logyの、というか、田原さんの料理の特徴は2つある、と思った。
ひとつは「日本人のシェフが台湾で作るフランス料理」であること。
もうひとつは、田原さん自身の個性だ。
logyは、先ほど述べた「A どこの国で」「B どこの国の人が」「C なに料理を作るか」が3つとも異なる例となる。
3つの要素がすべて異なるとどうなるかというと、それぞれの国や地域の、食文化や食材(logyの場合はフランス・日本・台湾)がどんどん混じってくる。
かけ合わせの種類が、2つだったときよりも飛躍的に増えるのだ。
そして、なに料理というカテゴリの重要さがうすれ、誰料理とでもいうべき料理に近づいてくる。
以前は「フュージョン料理」などといわれ、ともすれば揶揄されてきたこれらの料理は、もはや、そういうカテゴリの中にはおさまらなくなってきている。
フュージョン料理ともはや呼べなくなっている理由は、彼らの、それらの国の料理や自分のアイデンティティの突き詰め方が意識的だからだろう。
ベストレストラン50などで高評価を受ける店も多く、この流れは、今後ますます加速していくのではないかと思う。
田原さんに、ご自身の料理はなに料理だと思いますか?とたずねてみた。
長年イタリア料理をベースにしたのち、フレンチのお店で働き、台湾に来て何料理を作っていくのかということを考えた時に、台湾と日本人の僕の共通点はアジアという同じフィールドにいるという答えしか無いと考えました。
やはり、ご自身の意識の中でも「なに料理」というカテゴリーではなくなっているようにみえる。
しいていえば、アジアンコンテンポラリーというような、ざっくりとしたくくりだ。
フランス・日本・台湾、3つの地域の要素の分け方が意識的だなと思ったのは、食材だ。
logyでは、食材は日本のものはなるべくいれず、台湾のものにこだわりたいのだという。
そうでないと、台湾でレストランをやる意味が薄れると考えているからなのだそうだ。
日本の食材がいくらでも入手できる現在において、思い切ったな、とも思う。
とはいいながら、logyの料理は台湾の方向にはあまり突っ走っていってない。
ここの料理が台湾とフランスと日本の微妙なバランスの立ち位置にいるのには、別の理由もあるとみた。
それが田原さん自身の個性だ。
スパイスの使い方が、どれも抑制的なのだ。
スパイスの味と食材そのものの味のバランスが、どちらかが強すぎない、どちらも弱すぎないような良い感じになっている。
田原さんは、台湾でlogyをオープンするまで、台湾中の小吃店で香りの要素を探し求めたのだというが、実はスパイス類があまり得意ではないのだそうで、それで今回の味にとても合点がいった。
台湾っぽく行き過ぎないという微妙なさじ加減の理由は、そのへんにあるのかもしれない。
いま、レストランにとって、場所の持つ意味が変わりつつあるのかもしれない。
かつて、レストランは「そこにあること」が絶対だった。
もちろん今でも、かなりの部分ではそうだろう。
その土地の気候に根ざした食材、そこから生まれた料理、そしてその場所ならではの物語。
それらが相対的になって、混ざってきているのが現代だなと思う。
なに料理かという料理のベースと、その人が肌で知る食文化と、作る国の風土や食文化。
この3つが混ざって、これまでにない新しいものが生まれる要素が大きくなってきているし、今後もより進化していく気がする。